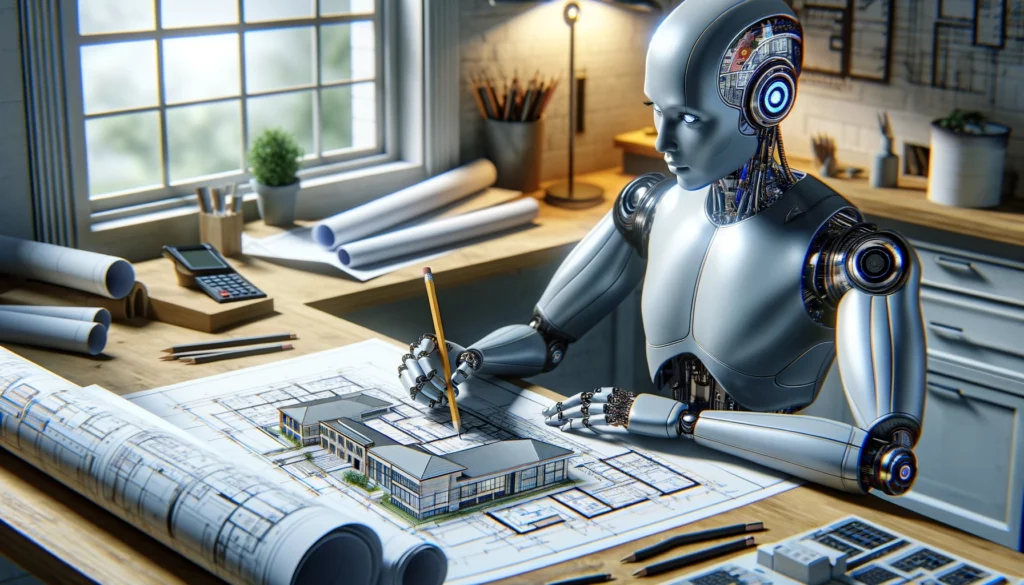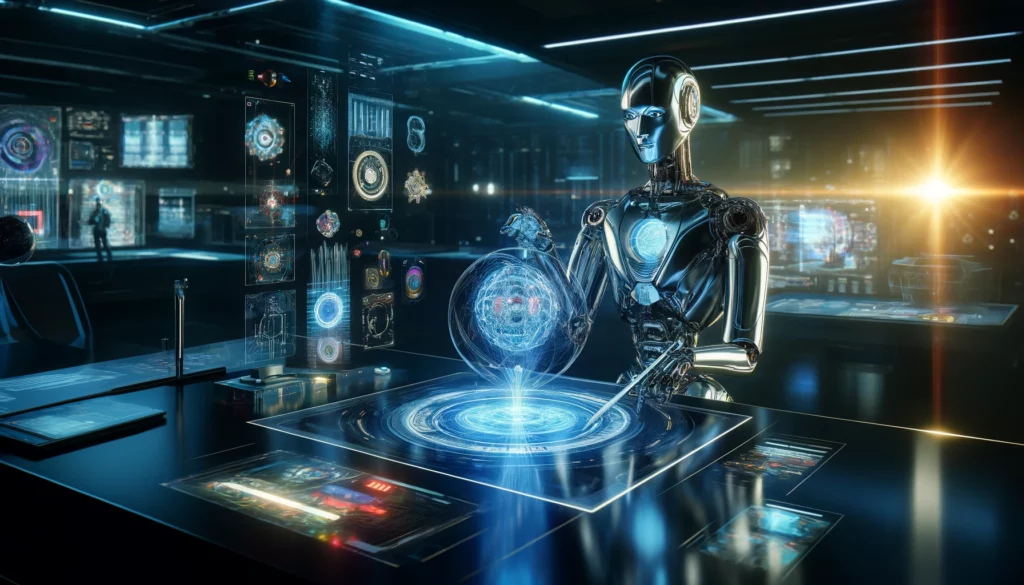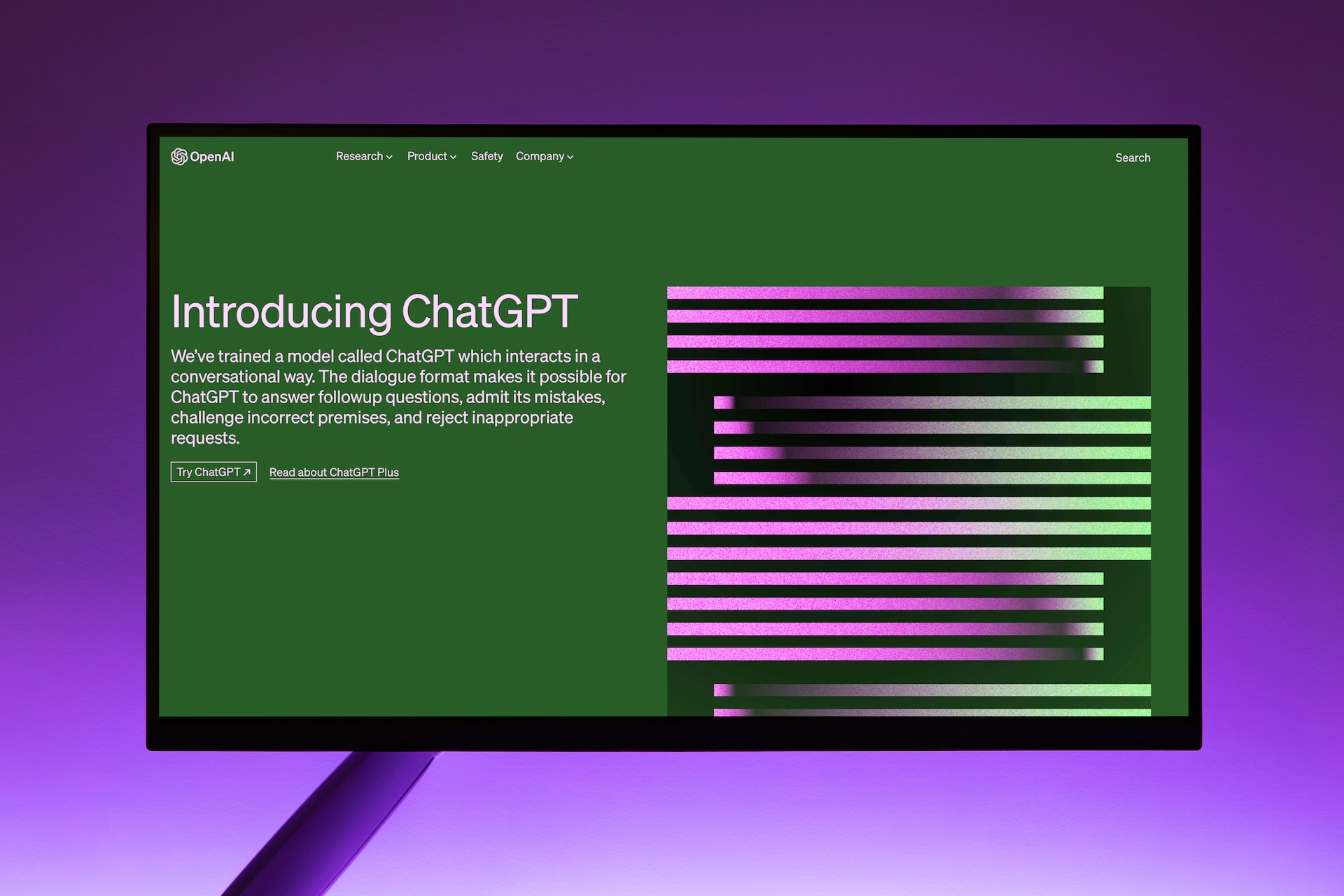
ビジネスシーンでは、様々なAIが導入されていますが、中でも使用されることが多いのはチャットボットです。顧客からの問い合わせ対応や、社内問い合わせなど、チャットボットが活躍できる場面が数多くあります。チャットボットを導入するためには、まず開発が必要です。では、具体的にどういった方法でチャットボットを開発するのか、どのような人がチャットボット開発に向いているのかなどを解説していきます。
▼もしAIを使った開発を検討している場合は、Automagica Labで無料の開発相談をしてみませんか?
目次
チャットボットの開発方法
チャットボットを一から開発しようとすると、高度なプログラミング技術や機械学習に関する知識が必要です。ただ、比較的簡単に、チャットボットを開発できる方法もあります。
他社サービスを使う
他社が提供しているAPIサービスを活用すると、簡単にチャットボットを開発することができます。APIとは、システムの一部を外部連携できる機能です。そして、LINEやFacebookなど、一部のサービスは、チャットボットの機能をAPIとして提供しています。それを導入すると、簡単にチャットボットを使える環境を構築できます。APIによるチャットボット開発は、プログラミングのスキルを特に必要としないのがメリットです。
また、APIは提供していないけれども、チャットボットの骨組みとして使える、フレームワークを提供しているサービスも数多くあります。フレームワークを使用する場合、プログラミングは必要となりますが、骨組みが出来上がった状態から開発を進められます。そのため、一から開発するよりも、時間と手間を大幅に削減できるでしょう。
生成AIを使う
チャットボットは、ChatGPTなど、生成AI系サービスとしても提供されています。その機能をそのまま、独自のチャットボットとして活用するという方法もあります。ChatGPTであれば、APIによって、そのまま問い合わせ窓口として取り入れることも可能です。生成AI系サービスは、膨大な言語データを使用した、高度な学習を済ませています。そのため、より的確な回答ができる可能性が高いです。
チャットボットを使う前に検討するべきこと
チャットボットの開発や導入を始める前に、いくつか注意しなければならないことがあります。実際に開発が完了してからでは手遅れになる注意点もあるため、あらかじめ検討することが重要です。
チャットボット導入の理由
まず考えなければならないのは、チャットボットを使用する目的です。ひと口でチャットボットと言っても、細かな機能はそれぞれ異なります。そして、具体的な目的はひとつではありません。
単純な問い合わせ対応や、顧客の問い合わせデータの収集など、色々あります。その目的に適したチャットボットを開発することが重要です。必要な機能が搭載されていないチャットボットを用意しても、あまり役には立たないでしょう。
必要ない機能があるチャットボットの開発は、余計な時間やコストを発生させてしまいます。よって、何のためにチャットボットが必要なのか、目的を明確にしてください。その目的を達成できる、必要最低限のチャットボットを開発するようにしましょう。
また、そもそもチャットボットが必要かどうかを検討することも重要です。チャットボットは、万能なツールではありません。専門性の高い問い合わせには、対応できない可能性が高いです。
よって、専門的な問い合わせばかりが舞い込んでくる環境であれば、チャットボットを導入するよりも、専門教育を済ませた人を雇用した方が良いかもしれません。
チャットボットの運用体制
チャットボットは、ひと通りの開発が完了した状態で導入するのが基本です。ただ、導入しただけで、問題なく使い続けられるわけではありません。導入した後に、エラーを起こしたり、期待する機能を発揮できなかったりする恐れがあります。
そのため、稼働状況を確認しながら、調整を行わなければなりません。また、定期メンテナンスによる、必要ないデータの削除や異常チェックなども必要です。
チャットボットを導入するのであれば、具体的な調整方法やメンテナンスの頻度、担当者など、運用の内容はあらかじめ決めておいた方が良いでしょう。
導入後に運用体制を整えようとすると、担当者用の人材を確保できない、間違ったメンテナンスをしてしまうなど、トラブルに繋がる恐れがあるので要注意です。
チャットボットの育て方
チャットボットは、あらかじめ用意してある学習データを元にして、回答内容を作ります。そのデータ量が多ければ多いほど、回答の精度が高くなるのが特徴です。
ただ、データを増やすには、コストと時間がかかります。そのため、回答の精度と、コストあるいは開発時間を天秤にかけながら、どれくらいのデータ量を使ってチャットボットを育てるのか、検討しなければなりません。
また、導入後に、問い合わせ内容を学習データにして、自ら成長させるためには、高度なチャットボットを選ぶ必要があります。チャットボットの種類選びを間違えると、期待通りに成長してくれないかもしれません。
そういったことにならないよう、開発の初期段階で、チャットボットの育て方ははっきりさせておきましょう。その上で、チャットボットの導入計画を作っていくと良いです。
チャットボットを内製で開発するべきユーザー
チャットボットを導入する際に、外部のシステムやサービスを使うか、内製で開発をするか、迷う人は大勢いるはずです。そのような時は、自身が開発に向いているかどうかを確かめましょう。自身で開発をするべき人の特徴は、以下の通りです。
自社内にデータを溜めたい
チャットボットは、問い合わせ対応だけでなく、データの収集を目的として導入することも多いです。ビジネスにおいて、問い合わせやクレームの内容は、商品開発の材料になったり、顧客対応の改善に繋がったりします。
ただ、開発を外注したり、外部のチャットボットサービスを利用したりする場合、データの保存ができないことがよくあります。そのため、問い合わせの内容をデータベースとして溜めておきたいのであれば、チャットボットを内製で開発した方が良いです。そして、データを保存した上で、管理ツールと連携させられる機能を搭載させましょう。
ランニングコストを抑えたい
外部のチャットボットサービスを利用する場合、ランニングコストがかかります。特に、サービス提供側のサーバー上にあるチャットボットを使う、SaaS系サービスは、継続利用のために費用を支払い続けなければなりません。
支払いを止めると、その時点でチャットボットは使えなくなってしまいます。また、買い切り型のチャットボットも、開発者にメンテナンスや調整を依頼しなければなりません。そのため、どうしてもランニングコストが発生します。チャットボットを内製で開発し、自らメンテナンスを行うようにすれば、そのようなコストは必要ありません。よって、チャットボットのランニングコストを抑えたい人も、内製での開発を考えてみましょう。
生成AI系のサービスを使いたい
チャットボットの開発を外注したり、外部のチャットボットサービスを使用する場合、導入するのは開発者オリジナルのチャットボットです。場合によっては、回答の精度が低いかもしれません。ChatGPTのような生成AIの方が、的確な回答を出せる可能性は十分あります。
そのため、生成AIを、そのままチャットボットとして使いたいと考える人もいるでしょう。そのような人は、内製で開発をして、生成AI系サービスを導入すると良いです。高精度な生成AIを使える上に、外注や外部サービス利用のコストを抑えられます。
技術力があればチャットボットは内製で開発できる
チャットボットは、専門性の高いAIであるため、開発するには外注しなければならないと考える人は大勢いるでしょう。しかし、ある程度の技術力を身につければ、内製でチャットボットを開発することも不可能ではありません。したがって、何も考えずに外注するのは止めましょう。具体的な開発方法や注意点などを把握した上で、外注するか、内製で開発するかを決めると良いです。