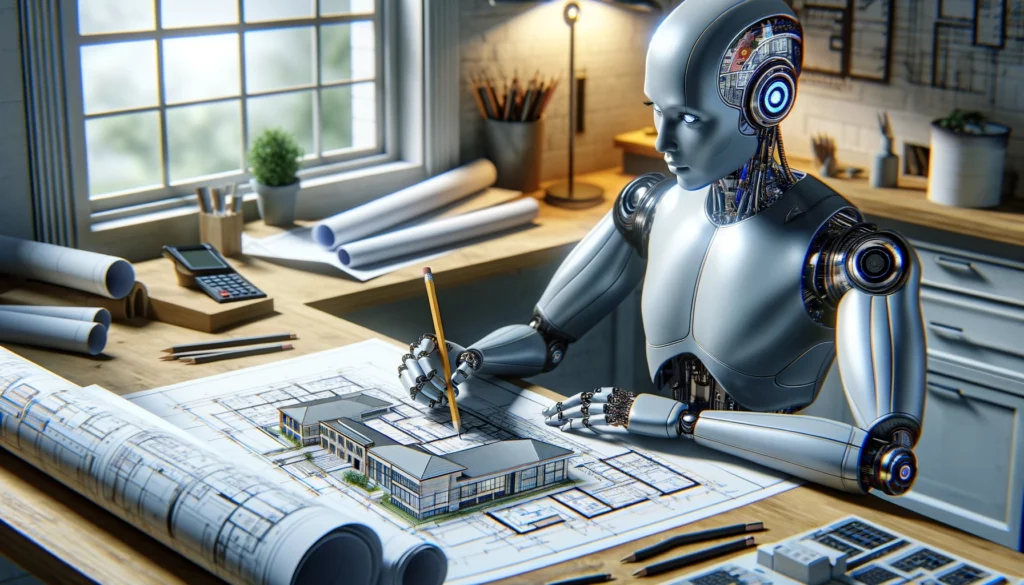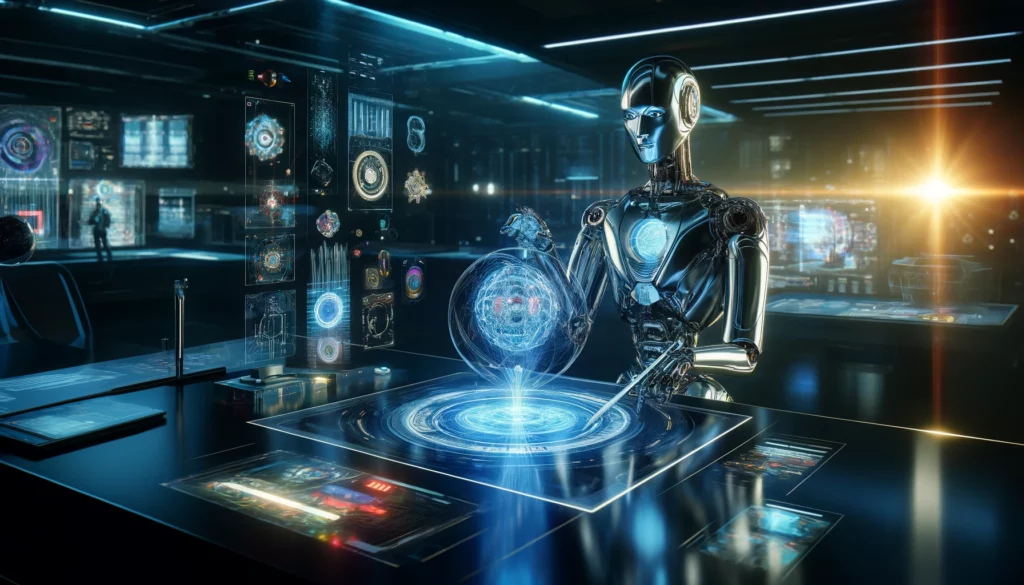近年では、様々な企業がビジネスにAIの活用を検討するようになっています。AIができることは年々拡大しており、有効に用いれば強力な業務効率化のツールとなるでしょう。今回はAIを用いた業務効率化について、事例を中心に解説します。また、業務効率化を目的にAIを用いる際の注意点も紹介しているので、AIを導入するときにはぜひ参考にしてください。
▼もしAIを使った開発を検討している場合は、Automagica Labで無料の開発相談をしてみませんか?
目次
AIを使った業務効率化とは
AI(人工知能, Artificial Intelligence)とは、推論や問題解決のような知的行動を、コンピューターを用いて実現するソフトウエアのことを意味します。21世紀以降のAIの発展はすさまじく、まるで人間のようなふるまいを見せるAIも登場するようになりました。
AIを用いた業務効率化とは、企業のビジネスプロセスや業務にAIを用いることによって、業務全般を改善させることを指します。うまくAIを用いれば人をはるかに上まわる作業処理能力によって、業務効率化を大きく推し進めてくれることでしょう。
なお、AIは学習のやり方次第で様々な業務に適用できるようにカスタマイズが可能です。そのため、多くの企業がAIの導入を検討するようになりました。業務効率化以外にも次のようなものがAIを用いるべき理由として挙げられます。
- 労働力不足をAIによって補完できる
- 危険な作業における労働者の安全性が向上する
- 24時間対応による顧客満足度の向上
- 仕事の属人化を防止する
- 高度なデータ予測や分析が可能
- 人が人ならではの業務に専念できるようになる
AIをビジネスに活用するメリット
AIをビジネスに活用することで得られるメリットは多岐にわたります。それぞれ、具体的な例とともに解説します。
定型業務の自動化
皆さんは普段、ルーティーンのように行なっている業務はないでしょうか?AIは定型業務の自動化に優れているので、AIを活用するのがおすすめです。
例えば朝に数値を確認し、レポートを作成して上司に報告する業務があったとしましょう。人間が行おうとすると数値の確認、レポートの作成、上司への報告の3つのステップが発生します。
AIに任せることで数値の確認及びレポートの作成を自動化できるため、人間が行う作業は上司への報告だけになります。単純作業だと1回1回の削減できる時間は短いかもしれませんが、チリも積もれば山となると言うように、長い時間で見ると大きな変化を生み出すことでしょう。
情報の分析
AIは人間をはるかに上回る分析能力を持っています。人間の場合、多くのデータがある場合、それを多角的な視点から見て分析することは難しいです。それは人間の脳みその限界があるからです。
逆にAIは計算できるコンピューターパワーさえあれば、データ量に関係なく分析することが可能です。
ただAIの分析は人間が行う分析と違って、数値や大局観を見ての分析になるため、詳細な分析においてはまだ人間の方が優れているかもしれません。
AIを使って業務効率化できた事例
実際に企業や自治体はAIをどのように取り入れて業務効率化を成功させているのでしょうか。以下では企業や自治体におけるAIの導入事例を紹介します。
AIチャットボット
チャットボット(チャッターボット)とは、まるで人間と対話するかのように、テキストや音声を使った会話ができるソフトウエアやサービスのことを意味します。AIを導入したチャットボットが誕生したことで、様々なシーンでチャットボット(AIチャットボット)が活用されるようになりました。
今ではAIチャットボットは業務効率化における強力なツールとなっています。AIチャットボットは主に、カスタマー業務や各種問い合わせ対応などに用いられています。
例えば、東京都世田谷区ではコロナウイルスの流行によって通常の問い合わせ業務が難しくなった時期に、AIチャットボットによる案内を開始しました。
状況がすぐに変化するので、人が受け答えをするには困難な状況が続いていました。ですが、AIを用いれば、変化が早い情報であっても、素早くキャッチでき、問い合わせに素早く正確に対応できます。
また、AIチャットボットなら24時間いつでも対応が可能です。現在では多くの自治体において、AIチャットボットによる問い合わせ対応が行われるようになりました。
AIチャットボットを、社内ヘルプデスクとして活用している企業も増えています。「担当者が受け答えしてもいいのでは?」と考える方も多いかもしれませんが、社内業務における他部署からの質問は意外なほどに数が多いものです。
同じ質問の対応を迫られる担当者の心理的負担となっています。AIチャットボットを用いれば、いわゆる「よくある質問」に対して、正確な情報を素早くかつ人の手を通さないで返答することが可能です。その結果、AIチャットボットは、担当者の負担を減らし、業務効率化に寄与します。
経費精算システムで知られる株式会社ラクスは、AIチャットボットの運用を開始することで、経理部の業務効率改善を達成しました。当該企業では月末時期になると、大量の質問が経理部門に寄せられ、本来の経理業務を圧迫するほどとなっていました。
AIチャットボットの導入によって、経理部が問い合わせ対応に割かざるを得なかったる時間を半分ほどに削減。マニュアルを確認すれば簡単にわかる質問については、問い合わせ件数が大幅に減少しました。さらに、AIチャットボットの導入後は、自分でマニュアルを確認する社員が増えました。経理部だけでなく社内全体における業務効率化も進んだと言えるでしょう。
生成AIによるクリエイティブ作成
生成AIとは、テキスト・画像・その他のメディアを、学習データを元にして自動的に生成するAIのことです。生成AIは従来のAIとは違い、クリエイティブな分野において新しいアイデアや独自コンテンツを生み出せます。
2023年時点において、世界で最も有名なAIといえるChatGPTは、生成AIの1つです。ChatGPTをコ文書作成に利用している企業は数多く存在します。
例えば、企業のブログ記事やレポートの自動作成に用いれば、文章作成にかかる手間と時間を大幅に削減できるでしょう。
横須賀商工会議所では、会員向けに店舗紹介文を作成できる、ChatGPTを利用したサービスを提供しています。このサービスでは簡単な情報を入力するだけで、店舗紹介文に加え、キャッチコピーと当店のおすすめを作成してくれます。これによって、店舗紹介に関する業務を簡易化し、業務効率化を成功させました。
また、デザインやアイデア出しに生成AIを用いる企業も少なくありません。これによって、製品開発のプロセスを大幅に短縮化できます。
株式会社プラグでは、生成AIによるサービスを提供しています。このサービスは、いくつかのデザインを登録することで、それを元に最大1000件のデザイン案を提示するというものです。加えて、登録したデザインの評価も自動的に行ってくれます。このサービスの導入によって、サービス利用業者だけでなく、株式会社プラグ自体も、デザイン評価に関する業務の効率化に成功しました。
契約書レビューの自動化
契約書レビューとは法的観点からの契約書のチェックのことを意味します。作成された契約書にリスクはないか、法的に問題はないか、有効かつ妥当であるか、などを調べます。リスクマネジメントとして契約書レビューは大変重要な過程です。
しかし、かかる手間や労力も大きいことが問題でした。けれども、近頃ではAIを使い、契約書レビューを自動化させることが可能になっています。
株式会社Link-Uの法務部では、契約審査業務に業務時間の25%から50%ほどをかけており、レビューの依頼が来ると返答に2日から3日ほどの時間を必要としていました。AIによる契約書レビューを導入した後は、当日中にレビューの返答が行えるまでに業務効率が改善しています。
加えて、レビューのために弁護士事務所へと依頼する件数が減ったことで、費用の圧縮もできました。なお、契約リスクをAIでチェックすることは、仕事へのストレスや不安を軽減させることにも役立っているそうです。
AIを使って業務効率化を狙う際の注意点
AIを導入する際には気を付けたい注意点が存在します。以下に注意点を3点紹介します。
目的を明確にする
AIを導入するにあたっては必ず目的を明確にしなければなりません。そうでなくては、AIの導入自体が目的となってしまい、無意味な支出を増やす結果となり兼ねないからです。自社が抱えている課題や達成したいゴールを明らかにし、AI導入の目的となる「業務効率化したい作業」をはっきりとさせましょう。
そのうえで、業務効率化したい作業がAIによって解決可能かどうか検討してください。解決可能であればAIを導入すると良いでしょう。AIの導入はあくまでも手段にすぎません。手段が目的と入れ替わらないように注意しましょう。
AIに任せっきりにならない
AIはすべての業務をこなせる万能ツールではありません。思いのほか簡単な作業でつまずいてしまうこともあれば、人では到底不可能な作業を一瞬で終わらせることもあります。
得手不得手がはっきりと存在しているので、AIに任せっきりにならないように注意してください。ときには人が手を貸さなければならない状況が存在しています。
例えば、結論が入り組んでしまう問題では、最適な回答を出せないことがあります。学習に使ったデータが誤っている場合には、修正されるまでその過ちに気づかないことも珍しくありません。このようなケースでは、人がAIに代わって回答したり、人が正しいデータをAIに提供したりする必要があります。
長期的な目線で運用する
残念ながら導入したAIは最初から効率的に活用できるとは限りません。AIを効率的に活用できるようにするには環境に適した学習と、システムの見直しが欠かせないからです。
そのため、短期的な視点でAIの効果を判断すると、まるでAIの導入に失敗してしまったかのように見える場合があります。AIの導入を検討している場合には、長期的な目線での運用を念頭においてください。繰り返しシステムを見直し、新しいデータを学習させることで、AIは最適化していき目的とする結果を達成できるようになるからです。
多くの企業がAIで業務効率化を実現!ただし導入は目的を見極めてから
労働力不足の解消・労働者の安全性や顧客満足度の向上など、AIには用いるべき様々な理由があります。業務効率化もそのうちの1つです。多くの企業が業務効率化を目的にAIの導入を実現してきました。その結果、AIチャットボット・生成AI・契約書レビューなどで、たくさんの成功事例が報告されています。しかしながら、AIの導入はあくまでも手段にすぎません。導入する際は、手段と目的とを混同しないようにしてください。